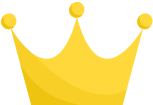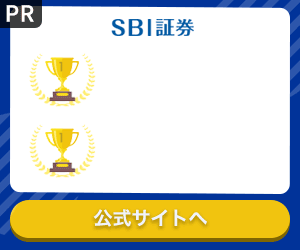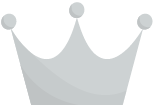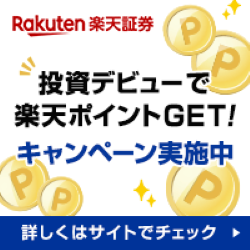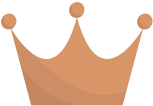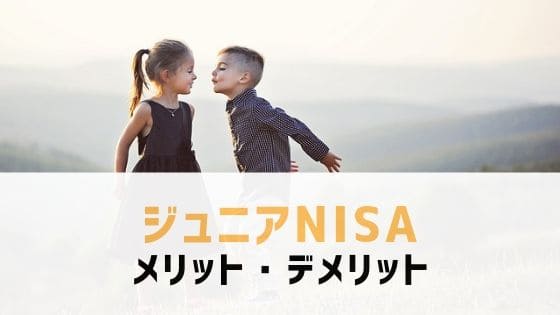こんにちは。FP2級のうちたけ(@uchitake_enjoy)です。
結論から言えば、我が家は学資保険とジュニアNISAを併用しています。
最初に学資保険に入り、次にジュニアNISAを始めました。
学資保険もジュニアNISAも一長一短あり、どちらが絶対にいい。というものではありません。
特にジュニアNISAは投資なので、元本保証ではありません。
だったら学資保険だけでいいんじゃないの?そんなにリスクをとる必要はないじゃん。
って思うかもしれませんね。
ただ、学資保険にもデメリットはあります。
現在の100円の価値が、将来にわたっても100円の価値があるかは分からないんですね。
???
と思うかもしれませんが、この記事では学資保険、ジュニアNISAのメリット・デメリット。
そして我が家が学資保険とジュニアNISAを併用している理由についてまとめていきたいと思います。
大学に進学したらいくら必要?
学資保険もジュニアNISAも、大学進学した場合に備えるための資金という性格が強い金融資産です。
学資保険は18歳ころから学資金が支給されるように設定されているものも多いですし、ジュニアNISAも18歳までは払い出し制限がありますよね。
つまり、大学費用が膨大にかかるので、それまでにお金を貯めておきましょう。というのが主な趣旨になります。
では、具体的に大学に進学したらいくら必要なのでしょうか?
国立で500万、私立理系で1,200万
大学在学時にかかる費用は、自宅通いか否か、公立か私立か、文系か理系かによっても変わってきます。
大学4年間でかかる学費・生活費はいくら?によれば、
国公立×自宅通いで500万円強、自宅外であれば1,000万円弱かかるとされています。
また、
私立文系×自宅通い=730万円
私立文系×自宅外=1,130万円
私立理系×自宅通い=830万円
私立理系×自宅外=1,230万円
となっていて、結構恐ろしい額がかかることが分かります。
教育資金はコツコツと計画的に
大学進学する時にいきなりこの額は用意できませんので、子供が小さいうちからコツコツと資金準備しておくことが重要になってきます。
全てをカバーできなくても、ある程度まとまった額は必要になりますよね。
学資保険だけで充分か?リスクはないのか?

ある程度まとまった金額を準備するために「学資保険」という選択肢があります。
有名なのでご存知の方も多いでしょうし、実際に始めている方もいると思います。
子供が「何歳から始めるのか」「何歳までに払い込むのか」にもよりますが、だいたい200万円の学資金を受け取るために、毎月10,000円くらいの保険料がかかります。(18歳までの払い込みの場合)
毎月10,000円の捻出が難しい方もいるかもしれません。
しかし、子供手当などを学資保険料にあてることで学資保険料を捻出できる場合もありますよね。
子供が大学に進学するまでに200万円を用意できれば、十分とは言えないものの貴重な軍資金になるのは間違いありません。
学資保険のメリット
学資保険は利回りが悪すぎる。ということで敬遠される場合があります。
特に利回りを気にする投資家なんかにはボロカスに言われますね。学資保険なんて必要ないと。
例えばソニー生命の学資保険の場合、払い込み期間が18歳までで、200万円の学資金を受取る場合、払い込み総額が193万円になります。
193万円支払って、200万円のリターンです。
返礼率は103.3%です。7万円しか増えません。
これは感覚ですが、7万円も増えるのか。増えるならいいじゃん。と思った方もいるかもしれません。(最近は環境が悪く、払い込み総額を下回ってしまう学資保険もあるようです)
ですが、投資の感覚からすると18年も運用して7万円しかリターンがないのは「割に合わない」と思ってしまうわけです。
私も昔はそう思っていました。
ですが、学資保険の本質は「増やすこと」ではないと思っています。
学資保険は返礼率の高さをアピールするケースが多いです。正直、そのくらいしかアピールポイントがないからですね。
ですが、返礼率なんて、ほとんど誤差です。
ではなぜ学資保険がいいのか?といえば、それはやはり「保険」だからです。
何言ってんだこいつ?保険?当たり前じゃん。
って思うかもしれませんが、重要なポイントなんですよね。
つまり、考えたくはないですが「自身の身に何かあったとき」子供の教育資金に困らないようにするための「保険」なわけです。
学資保険は万が一、契約者が亡くなった場合、保険料の払い込みが免除されます。
一方で保障は継続され、契約時に約束された学資金は100%受け取ることができます。
貯金でも投資でも、毎月コツコツ貯めていくことが前提となります。このまま〇〇円貯めていったら、10年後にいくらになるな。とか計算しながら貯めるわけです。
ですが、万が一、貯金(や投資)をしている人が亡くなってしまったら、その計画は崩れてしまいますよね。
亡くなった時点で貯金や投資の原資がなくなるわけです。
一方、学資保険は万が一の時は払い込みが免除され、契約時に約束された学資金が保証されます。
これは、学資保険の最大のメリットです。
万が一の時なんか、正直考えたくはないですけどね。転ばぬ先の杖、ということです。
学資保険の意外な落とし穴とは

一方、学資保険にも落とし穴というか、気を付けておかなければならないことがあります。
それは、インフレリスクです。
例えば、現在の100円の価値は、将来にわたっても100円の価値であり続けるでしょうか?
そうであるかもしれないですが、そうでない場合の方が可能性としては高いかもしれません。
ここ最近、デフレ、デフレと言われていたので物価が下がることを経験している人も多いと思います。
一方で、(うまくいっているか否かは置いておいて)安倍政権は2%の物価上昇(インフレ)を目標としていることも知っている方もいると思います。
つまり、モノの価値(値段)というのは常に一定ではないんですね。
ここに学資保険の落とし穴があります。
学資保険は、例えば〇〇年後に200万円を保証します。という類の金融商品です。
現在の200万円の価値と、将来の200万円の価値は違いますよね。
物価がも上がり、現在100円で買えたものが、20年後は200円出さないと買えない世の中になっているかもしれません。
つまり、大学費用も上がっている可能性もあるわけです。
事実、多少古いデータではありますが、文部科学省の調査によると、国立大学および私立大学の授業料は年々上昇していることが分かります。
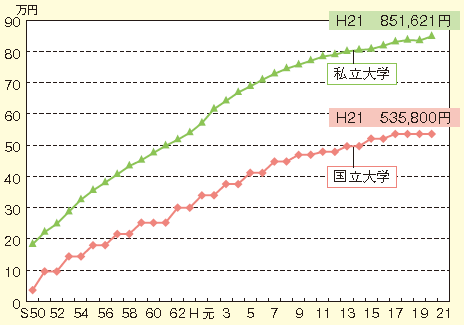 大学の授業料は年々上昇している(引用:文部科学省「家計負担の現状と教育投資の水準」より)
大学の授業料は年々上昇している(引用:文部科学省「家計負担の現状と教育投資の水準」より)物価も緩やかに上昇していますが、授業料はそれ以上に上がり続けていますね。
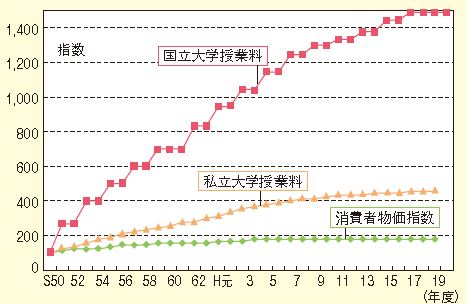 消費者物価指数も緩やかに上昇するも、大学費用の上がり方が大きい(引用:文部科学省「家計負担の現状と教育投資の水準」より)
消費者物価指数も緩やかに上昇するも、大学費用の上がり方が大きい(引用:文部科学省「家計負担の現状と教育投資の水準」より)つまり、先に書いた大学の授業料である、国立(自宅通い)で500万円、私立理系(自宅外)1,200万円というのは現在の価値をベースにした価格であって、将来は上がる可能性もあります。
学資保険が200万円あるからある程度安心。と思っていたら、将来、200万円じゃ全然足りない。想定外だ!ということもあり得ます。
これは学資保険が悪い。というわけではなく、学資保険というのはそういう性質のものであり、きちんと頭に入れておく必要があることなんですね。
ではどうするか?と言えば、インフレリスクに比較的強いと言われている「投資」を併用しては?ということです。
具体的に言えば、ジュニアNISAですね。
ジュニアNISAは元本保証ではないが
当然ながら投資ですので、ジュニアNISAで投資したところで元本が保証されるわけではありません。
ただ、長期的に投資を考えるのであればある程度のリターンが期待されます。(何度も言いますが、元本保証ではありません)
どの程度の利回りを見込むのか?
例えば私たちの年金を運用している機関であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)という組織があります。
たまに年金の運用利回りがマイナスになった時に野党にやり玉に挙げられる組織ですね。
投資なので、利回りがマイナスになる年もあれば、プラスになる年もあります。
長期的に見てプラスになるような運用を目指しているので、短期的にマイナスになったタイミングでの批判はナンセンスだよなぁ・・。と思いながらマスコミの報道を見ています。
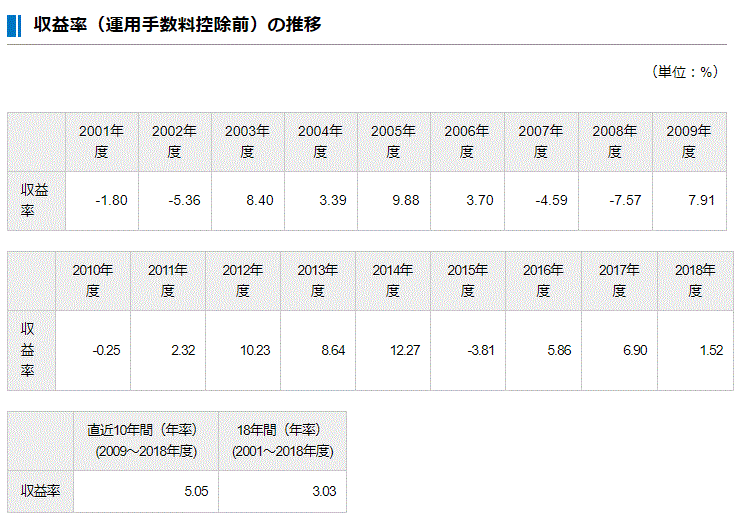 GPIFの利回り(引用:GPIF「運用実績はどのような状況ですか」より)
GPIFの利回り(引用:GPIF「運用実績はどのような状況ですか」より)実際、上の表を見れば明らかですが、年によってはマイナスの年があるものの、平均すると直近10年間の収益率(年率)は5.05%、リーマンショックの年も含む直近18年間の収益率(年率)を見ても3.03%の収益率を実現しています。(GPIF「運用実績はどのような状況ですか」より)
話が脱線しましたが、このGPIFという組織、運用利回り(名目)の目標を3%程度としています。
実際に直近18年間の年率も3.03%なので目標通りに運用できていると言えますね。
で、仮に私たちも投資において年率3%で運用できたとします。
※プロが3%なんだから素人が3%で回せるの?と思うかもしれませんが、GPIFは運用ポートフォリオを開示してくれています。そのポートフォリオ構成を真似すれば、それを実現することも比較的容易ですし、そもそもGPIFは「堅め」の運用をしているのでそれ以上のリターンも期待することはできます(一方リスクもあります)GPIFのポートフォリオはこちらに書いてあります。
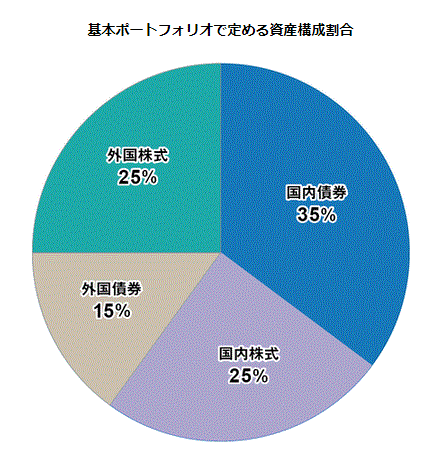 GPIFの基本ポートフォリオ(引用:GPIF「基本ポートフォリオの考え方」より
GPIFの基本ポートフォリオ(引用:GPIF「基本ポートフォリオの考え方」より利回り3%で運用した場合
毎月1万円、コツコツと18年間年率3%で運用できたとしたらいくらになると思いますか?
まず、原資は1万円×12カ月×18年間で216万円です。
実際に金融庁のツールでシミュレーションした結果がこちらです。
 毎月1万円、3%の利回りで運用できた場合(出典:金融庁「資産運用シミュレーション」より)
毎月1万円、3%の利回りで運用できた場合(出典:金融庁「資産運用シミュレーション」より)運用益はなんと、約70万円になります。元本と運用益の合計が約286万円になるんですね!
これが複利の効果です。もちろん、年によっては運用がマイナスになる年もあるでしょう。平均利回り3%でシミュレーションすると、このくらいになる可能性があるということです。
ただ、何度も言いますが投資は元本保証ではありません。仮に18歳になる年にリーマンショックのような不況がぶつかってしまった場合、資産が大きく棄損してしまう可能性があることは頭に入れておく必要がありますね。
※ジュニアNISAは2023年までの制度です。2024年以降の方針については後述しています。
我が家の場合、学資保険と預金、ジュニアNISAを併用しています
学資保険、ジュニアNISAのメリット・デメリットを意識しつつ、我が家ではそれぞれを併用しています。
預金も含めて3つを併用しています。
当然ながら預金は自身に何かあった場合のリスク(その後積み立てられないという意味で)もありますし、インフレリスクにも弱いです。が、流動性は高い(現金が欲しい時にすぐに引き出せる)というメリットはあるので、預金も併用しています。
我が家の目標額
目標としては、大学に入学するまでに500万円を用意することです。
学資保険で200万円、預金で200万円、ジュニアNISAで100万円作ることを目標にしています。
学資保険は18歳までの払い込みで1カ月1万円程度、預金も月1万円程度、ジュニアNISAは月5,000円程度を積み立てていってます。合計で月2.5万円です。
預金であれば、約17年で200万円が確保できる計算ですね。
ジュニアNISAは2023年までの制度なので
現時点の制度では、ジュニアNISAは2023年開始の投資までが非課税で運用できることになっています。
そのため、2024年以降はジュニアNISAの制度ではなく、通常の投資として運用をしていく予定です。
また、ジュニアNISA(および通常投資)の場合、3%の利回りで想定すると、14年程度で100万円が確保できる見込みで計算しています。(単純計算)
当然ながら、ジュニアNISAの制度が終了した後は課税される投資になるので税金分を考慮する必要がありますが、あくまで目安として想定しているものです。
学資保険とジュニアNISAはどっちがいい?まとめ
併用するのがベターだと私は思います。
ただし、どちらも一長一短あり、デメリットが重なってしまった場合にはちょっとやだなぁ。という感じはしますが、なんとかなるかな。と気軽な気分で考えてます。
将来のことは分からないですしね。楽観的に考えつつ、悲観シナリオもある程度想定しながらいこうかな。と思っている次第です。
ジュニアNISAのメリット・デメリットについては以下の記事でまとめています。
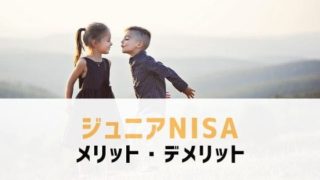
ジュニアNISAおすすめの証券会社で口座を開設する
ジュニアNISAにおいては、親権者が総合口座を持っていないとジュニアNISAの口座開設ができません。口座を持っていない場合は、まず親権者の口座開設をしましょう。
選べる投資信託の数も多く、自分にあった銘柄を見つけることができると思います。
ジュニアNISAではネット証券で唯一、海外株式の売買も可能です。
| おすすめ度 |
|---|



投資信託の数もトップクラスのラインナップを誇ります。
管理画面も使いやすく、簡単に投資の設定をすることができます。
| おすすめ度 |
|---|



| おすすめ度 |
|---|