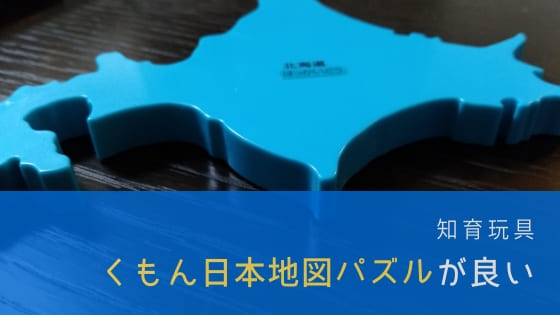こんにちは。知育玩具好きのうちたけ(@uchitake_enjoy)です。
私が知育玩具好きでも仕方がないのですが、子供たちも比較的楽しく遊んでくれていると思います。
今日は知育玩具でもモンテッソーリ教育で使われている「ピンクタワー」についてご紹介します。
 モンテッソーリ教具、ピンクタワー
モンテッソーリ教具、ピンクタワーモンテッソーリ教育を知ったのは、藤井聡太七段が小さいころモンテッソーリ教育を受けていたと聞いたのがきっかけです。
モンテッソーリ?なんだそれ?と思った記憶がありますが、調べていくうちに、なかなかいい教育法だな。と共感をしました。
モンテッソーリ教育を受けた著名人は特に海外で多いのですが、オバマ元アメリカ大統領や、イギリス王室のウィリアム王子やヘンリー王子。
起業家だとマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ、フェイスブック創業者のマークザッカーバーグ、アマゾン創業者のジェフ・ベソスなど名前を挙げるだけですごい人たちがモンテッソーリ教育を受けています。
わが子にそんな著名人になってほしいとか、そういう希望は特にないです。もっとも、将来のことは本人の人生なので、親が強制するものではないと思っています。
ただ、教育方法の一つとしてモンテッソーリ教育(の考え方)を取り入れてみようかな。と思った次第でして、その一環として「ピンクタワー」を購入したのでした。
■関連リンク(知育玩具)
✓藤井二冠も愛用したという知育玩具「キュボロ」の代替品
→Vallowスタンダードレビュー。キュボロとの違いは?品質はどう?
✓本格的な「立体」日本地図パズル
→4歳児が「くもんの日本地図パズル」で都道府県名を覚えられました
モンテッソーリ教育とは?
モンテッソーリ教育は、イタリアの医学博士、幼児教育者であるマリア・モンテッソーリ博士が考案した教育法です。
「子どもには、自分を育てる力が備わっている」という「自己教育力」の存在がモンテッソーリ教育の前提となっています。
モンテッソーリ教育の目的は、
「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てる」こと -日本モンテッソーリ教育総合研究所より引用
となっています。
私は「生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てる」という点に特に共感しました。
我々の将来もそうですが、特に子供たちが大人になったころ、もっと世界は変化していると思います。しかも、技術の進化によって、変化のスピードはさらに早まることが予想されます。
そんな時に、自分で考えて行動できないようでは、時代の変化に取り残されていってしまいます。
やはり重要なのは、常に学び、自らを変えていく力なのではないかな。と思っていて、親としてはそういう大人になってほしいな。とひそかに思っております。
ピンクタワーとは
 ピンクタワーとは
ピンクタワーとはピンクタワーは文字通り、ピンクに塗られている10個の木製の立方体です。
それぞれの立方体の大きさは違っていて、最も大きい立方体は1辺が10cmです。1cmずつ小さくなっていき、最小の立方体の1辺は1cmです。
一番大きな立方体となると、大人がもっても結構重く、かなりずっしりしています。
一番大きな立方体を土台に、一回り小さい立方体を順に積み上げていくことで、3次元の大きさの変化をとらえたり、「大きい」「小さい」といった概念を学べるようになっています。
なぜピンク色なのか?
なぜピンク色一色なのでしょうか?子供用のおもちゃであれば、もっとカラフルの方が楽しそうですよね。
でも、ピンク色一色には意味があるんですね。モンテッソーリ原宿子供の家の保育士、堀田はるなさんによる「子供の才能を伸ばす最高の方法ーモンテッソーリメソッド」によれば、
教具はどれもひとつの目的のためだけに作られています。
(中略)子供の家の教具の場合は、刺激はひとつに絞られていて、その他の刺激が排除されるような作り方がされています。
(中略)ですから、タワーを構成する10個の立体はすべて「立方体」で、色は「ピンク一色」だけに統一されています。これは活動のねらいを考えたうえでの配慮なのです。もしも、見た目の華やかさだけを考えて積み木のそれぞれに赤や黄色、ピンクなどさまざまな色を使ってしまえば、子供の興味はいっぺんに色のほうに向いてしまうでしょう。ー子供の才能を伸ばす最高の方法ーモンテッソーリメソッド(堀田はるな著)より引用
と書かれています。
味気ない感じもするピンクタワーですが、色、形それぞれに意味があるんですね。
ピンクタワーの目的・効果
3歳から6歳までは意識の芽生えの時期
3歳から6歳までの後期は、「意識の芽生え」の時期と呼び、前期に無意識に吸収したさまざまな事柄を、意識的に整理、秩序化していく時期とされています。
子供の自己教育力を発揮させる環境として、主に以下の5つの教育分野が用意されています。
日常生活の練習
感覚教育
言語教育
算数教育
文化教育
ピンクタワーは、上のうち、「感覚教育」を培う目的で用意されている教材です。
感覚教育とは
前述した「日本モンテッソーリ教育総合研究所」のWEBページによると、
意識して感覚器官を使って練習するのが『感覚教育』です。練習によって感覚器官が洗練されれば、外界からより精確でバラエティに豊んだ情報を収集できるようになり、知性や情緒が発達します。
また、感覚教具には、「対にする」「段階づける」「分類する」という、三つの操作が位置づけられています。このことによって、まさに脳の前頭葉が働き始め、知性が芽生え始めた時期の子どもは「ものを観察する能力」と「ものを考える方法」とを身につけることになります。
となっています。
確かに子供は3歳にもなるとそれまでの赤ちゃん~幼児未満のころとは違い、いろいろなことを観察し、気づき、親を驚かせることも多くなってきますよね。
母親が髪を切ったときなど、父親より早く気づくなんてこともあります(というか父親(私)は気づかない・・)
実際にピンクタワーで遊んでみた
ピンクタワーを買ったのは娘が3歳になったばかりの頃です。
やはりはじめての時は、私が見本を見せてもうまく積むことができず、大小関係なくバラバラに積んでいきました。
 はじめの頃はこんな感じ
はじめの頃はこんな感じ積めなくなったら終わり。って感じですね。
4歳にもなると、うまく積めるようになり、成長を感じることができます。
今はもうすぐ2歳になる息子が適当に3~4個積んで壊すという遊びをしていますが、それでいいかな。と思ています。
単純なおもちゃだけに、長く使うことができる教具かな。と思いますね。
ピンクタワーの注意点
 ピンクタワーを横に並べた感じ
ピンクタワーを横に並べた感じ前述しましたが、一番大きな立方体はけっこうずっしりして重いです。
最初のころはバラバラに適当に積みますので、崩れた時に少しあぶないというか、あたったら痛いです。
また、小さい積み木は1cm立方なので乳幼児は誤飲の恐れがあります。
いずれにしても、子供が小さいうちは親が見守りながらいっしょに取り組むのがいいかもしれません。
また、ピンクタワーにはスタンダードのタイプと、小さいタイプのものがあります。
おうちの状況に併せて購入することをおすすめします。
値段も全然違いますしね。